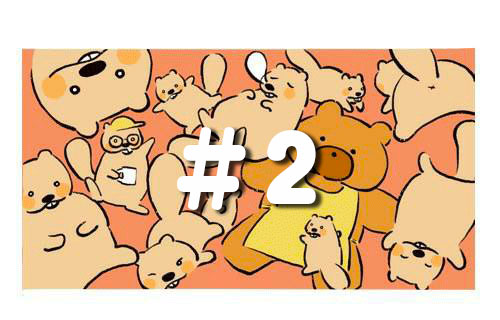【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #3
著者・野元
あっ、くまだ
路地裏を少し入った先に、本当に黒猫が待っていた。わたしを見ると、くじを咥えた口で器用に、にゃあと可愛い声で鳴いた。
「……かわいい」
わたしは黒猫の傍までいき、額を撫でようと恐る恐る手を伸ばした。すると黒猫の方から首を伸ばして、わたしの手の平にすりすりと額をつけてくれた。
「……かわいい!」
ゴロゴロと甘えてくる黒猫の足先を見ると、足先だけ白い毛色をしていた。
「足先だけ白いんだね、オシャレさんだね~」
両方の前足をふにふにと触ると、黒猫は地面に寝転んだ。にへへと気持ちの悪い笑い声が漏れてしまう。いつぶりだろう、自分の笑い声を聞いたの。そのまま黒猫を撫でまくる。
「……ねえ、良かったら、そのくじ返してくれるかな。正直わたしはどうでもいいんだけど、いまだったら、あの男の人に渡せるかもしれないし」
そう言って黒猫の口に手を伸ばすと、黒猫はすくっと立ち上がり路地裏を歩き始めた。どうも返してはくれないらしい。
「にゃあ」黒猫は振り返ってわたしを見ている。ついてきて、そう言われた気がした。
仕方がない。わたしは黒猫の後を追った。
路地裏を抜けると住宅街に出た。電柱には【押鴨比良坂一丁目】と書かれている。
知らない地名だなと思ったが特に気にならなかった。そのまま、見知らぬ住宅街を歩き、十字路を四回ほど曲がった頃、黒猫はとある建物の前で立ち止まった。
何かのお店だろうか。ネズミのような絵が描かれた木製の丸い看板が入り口軒先に吊るされている。店の前では大きなクマのぬいぐるみが椅子の上に置かれていた。
店は営業しているのだろうか。中は暗くてよく見えない。
黒猫は「にゃあ」とわたしを見た。
「どうしたの?」としゃがむと、咥えていたくじを離した。風で飛びそうになるくじをわたしは慌ててキャッチすると、黒猫はクマのぬいぐるみに向かって「にゃーにゅー」と鳴き始めた。
「このくまさんがどうかしたの?」
わたしは不思議に思って、クマのぬいぐるみの手を握った。
「すごい、もふもふ。……かわいい」
わたしはなんだか嬉しくなって、クマのぬいぐるみの頭を撫でたり、思わず抱きついたりした。そういえば、わたしってこういうの好きだったな。学生の頃、実家のベットはぬいぐるみで溢れていた。
そんなことを思っていると胸の中から「うーん、苦しい……」と声がした。
わたしは驚いて飛び退いた。わたしの前ではクマのぬいぐるみが目をこすりながらあくびをしている。
「お客さんかな。いらっしゃい。」
「うそ、ぬいぐるみが喋ってる……。なにこれ、ドッキリ……?」
黒猫はクマのぬいぐるみに挨拶するように「にゃあ」と鳴いた。
「おや、影猫じゃないか。珍しいなぁ、久しぶりに見たよ」
「かげねこ……?」影猫と呼ばれた黒猫はわたしの足下をスリスリと回った。
「そう、影猫。家を守る精霊でね、まぁ座敷童子みたいなものかなぁ。基本的に大きな屋敷や蔵に居つくんだけど、人に懐くのは珍しいね」
「ただの猫じゃないんだ……」
「普通の人には見ることもできない存在だよ。それで君はどうしたの?」
「わたしはこのくじを黒猫にとられちゃって。返してもらうために黒猫の後をついてきたんです」
わたしはクマのぬいぐるみにくじを見せた。すると、クマのぬいぐるみは目を丸くして「半吉のくじか。これまた珍しいね。……よく見てもいいかな?」
「別にいいけど……」クマのぬいぐるみにくじを手渡すと、しげしげと興味深げにくじを見ていた。
「半吉のくじってなんですか」
「……このくじは色々な呼ばれ方があるけど、僕は半吉のくじって呼んでる。半吉っていうのは、吉と凶の半分ずつって意味で、つまりは吉凶どちらになるか分からないって意味さ。このくじには膨大な運が集約している。宝くじの一等を引く以上の運がこのくじには入っているんだ。だけど、それをどう使うかは本人しだい。使う人によって幸福にも禍にもなるんだよ」
「よく分かんないんだけど……」
「このくじはとても珍しいもので、これを引いたのはとても幸運だってこと。でも、使い方によっては不幸にもなるから気を付けてね」
クマのぬいぐるみのぬいぐるみは椅子から降りた。背丈はわたしの腰くらいだ。
「僕はくま吉。君の名前は?」
「わたし? わたしは森谷しおり」
「しおり、いい名前だね。このくじは返すよ、見せてくれてありがとう。お礼にお茶でもしていかないか。ここまで来るのに大変だったでしょ」
「え、いいの……?」
たしかに今日は歩いたり走ったりして疲れた。休みたいのは事実だけど、自分が変な世界に足を踏み入れてしまっているのも事実。わたしが決めかねていると、くま吉が店の扉をガチャリと開けた。
「うちはカフェなんだよ。美味しいお茶を出すからぜひ飲んでいって。大丈夫、帰り道も教えるから安心してよ」
わたしはなんとなく足元の影猫を見た。影猫は行ってきなと言うように「にゃあ」と鳴いた。
「あなたも入る?」わたしはしゃがんで影猫に尋ねると、影猫はわたしの膝に一度頬ずりして、近くの電柱の影に飛び込んで消えてしまった。
「消えちゃった……」
「猫は気まぐれだからね。影猫はああやって影のなかを移動するんだよ。さあ、お入り」
「お、お邪魔します」
わたしはおっかなびっくりとお店のなかに入った。
文/著者 プロフィール

-
押上でハーブティー専門店ウッドチャック(カフェ)を営む。
詩、小説を書くのが趣味で、自分の本を出版するのが夢。
※「押鴨町のとあるカフェ」はウッドチャックをモデルにしておりますが、実在のお客さま、スタッフ、関係者は登場しません。
最新記事一覧
 読みものがたり2024年5月9日【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #4
読みものがたり2024年5月9日【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #4 読みものがたり2024年2月26日【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #3
読みものがたり2024年2月26日【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #3 読みものがたり2024年2月10日【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #2
読みものがたり2024年2月10日【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #2 読みものがたり2024年1月25日【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #1
読みものがたり2024年1月25日【連載小説】押鴨町のとあるカフェ #1